提供:日本電気株式会社(NEC)
NECヘルスケア・ライフサイエンス事業部門は、ヘルスケア領域などにおける60年以上の経験と実績を生かし、医療データの利活用事業に本格参入した。医療機関や製薬企業だけでなく、さまざまなデータ事業者などを受け入れて利活用基盤を強化し、電子カルテから収集した高品質なデータを構造化・標準化し、循環させることで、ヘルスケアとライフサイエンス領域における新たなサービスや価値の創造をめざしている。NECが医療データ利活用事業に参入する目的や、AIを含めたデータの利活用で医療機関や製薬企業がどう変わるのかについてお話を伺った。
ドラッグロスなどの社会課題を解決する
1966年に発売した日本初のレセプトシステムを皮切りにNECは長年にわたり、医療機関を中心にヘルスケア・ライフサイエンス領域でさまざまな事業を展開してきた。ヘルスケア領域では、電子カルテやオーダリングシステムなど医療機関の情報システム化の一翼を担い、近年では生成AIを搭載した電子カルテの提供などDX化支援に注力している。一方、ライフサイエンス領域では2019年に創薬事業への参入を発表し、現在AI創薬やがん最適治療法選択支援などに取り組み始めたところだ。
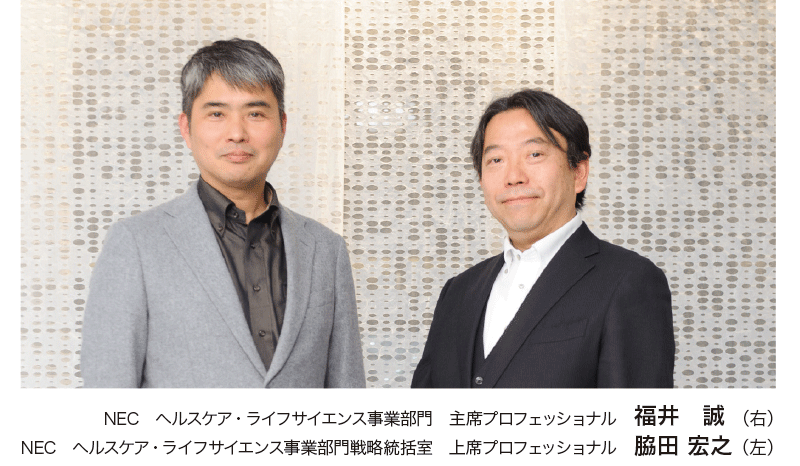
今回の医療データの利活用事業は同社で培われてきた技術やノウハウを基に、「質の高い医療・健康データが安心・安全に循環される環境・社会」を実現することによって、個々に最適な医療・健康サービスの提供や、創薬・医療機器開発への貢献などをめざしている。同社ヘルスケア・ライフサイエンス事業部門の主席プロフェッショナルである福井誠氏は次のように説明する。
「社会保障費の高騰や人手不足などを理由とした医療現場の負担増大、新薬開発ではドラッグロスなど、医療や創薬の現場はさまざまな社会課題への対応が求められています。NECではヘルスケアとライフサイエンスの2つの事業を両輪としたデータ利活用の推進により、医療機関や製薬企業、患者さんに向けてさまざまなサービスや価値を創出し、社会課題の解決に取り組んでいます」
データ利活用事業の大枠は、医療機関から得られた一次データを標準化し、医療の高度化だけでなく製薬企業における創薬・治験、国の医療政策などにも二次利用できるようにしていくというもの。同事業を支えているのがNECヘルスケアクラウド基盤であり、「3省2ガイドライン」に準拠して高度なセキュリティを提供するほか、電子カルテデータ標準化(HL7 FHIR規格準拠)や複数メーカの電子カルテ連携の機能を備えている。「当社の電子カルテシステムは約1200の医療機関で使用されていますが、その診療データをクラウドで活用できるように標準化していくのがポイントの一つです。さらにわれわれの保有するデータだけでは十分ではないと考えており、他社の電子カルテデータも標準化して使えるようにしています」と福井氏は説明する。
クラウド基盤への他社参入を推進
加えて、電子カルテデータの二次利用によるサービスの開発や提供はNECだけで行うのではなく、医療DXのスタートアップ企業などが参加できるベンダーフリーのクラウド基盤になっているのも大きな特徴だ。「例えば、PHR(Personal Health Record)のベンダーは数多く存在しており病院ごとに扱うPHRが異なることもありますが、この基盤に参加していただければ異なるPHR間でも患者情報を交換できますし、共通に使えるデータが増えることで、その価値も上がります。当事業がめざしているのはデータ販売ではなく、集めたデータの質を高めて循環させることで日本の医療問題を解決していくということです」と、同じくヘルスケア・ライフサイエンス事業部門戦略統括室の上席プロフェッショナルである脇田宏之氏は明言する。
このようなコンセプトを描けるのは、NECが医療分野で積み上げた実績に加え、世界上位レベルで国内ナンバーワンのAI技術などを有しているからだ。特に医療データ活用の課題であるカルテの非構造情報を構造化する技術に長けており、それまでデータベースに入らないような医師が記載したテキスト情報を構造化して意味付けし、さらに匿名化することによって医療データとして実用化できる段階に入りつつあるという。
非構造情報の構造化で
治験の効率化などに応用
同社の医療データ利活用サービスは医療機関向けの経営支援や臨床支援からスタートし、次の段階として医療・製薬双方への治験支援、そして最終的にはドラッグロスの解消や希少疾患の創薬など国全体に寄与していくようなサービスを順次展開していく予定である。「今、まさに医療と製薬の双方に貢献できるサービス群を開発しており、一部提供を開始しています。有害事象報告サポートもその一つです」と脇田氏。市販後の有害事象報告はいまだに手作業によるものが多く、内容のチェックや書き間違いの修正などで双方に負荷が掛かるケースが少なくない。同社ではCDCS(臨床データ収集システム)のデータ引用機能を用いて1回の電子カルテ入力で半自動転記による有害事象報告書作成を実現し、大学病院での実証実験では報告に要する時間が半減できたなど大幅な効率化と記載の質向上が図れたという。
また、医療データの活用は患者の同意が前提でありその取得が手間となる場合が多いが、クラウド基盤と患者のPHRを連携させる過程で、“自然の流れで”適切に同意を取得して医療データを管理できる包括個別同意管理システムを開発した。現在、実証実験中で今年中にサービスの提供を開始する。
そして今、同社が注力しているのが、先述した生成AIによる医療データ活用のポテンシャル拡大である。テキストなどの非構造情報の意味を解釈し構造化してデータ化することにより、医療・製薬分野で文書生成や症例検索、意思決定支援などさまざまな応用が可能になるからだ。「実は電子カルテの中でも重要な情報は、症状が出た時期や薬の変更理由などのテキスト情報です。これらを医療データとして活用することで製薬企業の本質的な課題解決に役立てることができると考えています」と福井氏は指摘する。
例えば、薬剤データや文献などを構造化し、ナレッジグラフを構築することで創薬研究者の標的候補の探索を支援したり、新薬と相乗効果のある併用薬候補を予測したりするなどだ。ほかにも、カルテのテキスト情報と治験の組入基準/除外基準をリアルタイムで照合し、治験症例を効率的に探索していく技術も開発中である。もちろん、創薬関連だけでなく、MA部門や営業部門に対しても仮説検証や市況に関するアドホック調査、場合によってはローデータ提供などで情報提供活動などの支援も進めている。
「今あるデータを活用するだけでは事業も長続きしません。高品質な医療データを循環させることで新たなRWDやインサイトが生まれてくると思いますし、またそれを活用することによって新たな地平を開拓できると考えています。そのためには医療機関、製薬企業、そして他社を含めたステークホルダーがパートナーとなり、一緒にそういう世界をつくっていくことが大事だと思います」と脇田氏は話す。日本の医療を低コストでイノベーティブに変えていくためには、とかく個別的に取り組みがちな医療データの利活用を統合していくという意思や技術が必要ということだ。
お問い合わせ先

日本電気株式会社
ヘルスケア・ライフサイエンス事業部門
〒108-8556 東京都港区芝4丁目14-1 第二田町ビル
E-mail :
hls_contact@hls.jp.nec.com
ウェブサイト :
https://jpn.nec.com/healthcare/index.html